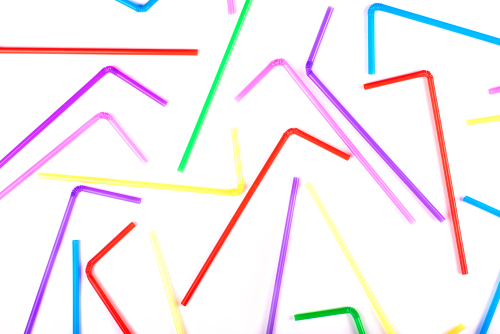-
[From April Issue 2013]

Non-Profit Organization, The Japan Return Programme
“To tell you the truth, I had no idea my mother was doing something so big,” says IKEZAKI Miwa, the executive director of a Non-Profit Organization, the Japan Return Programme (JRP). Miwa’s mother Miyoko founded the JRP in 1995 and ran it until last year when Miwa took over the reins. The purpose of the JRP is to nurture people who could one day forge important links between Japan and the outside world.
The JRP carries out two tasks. One is the “Nihongo Summit,” organized every year since 1999. It’s an event at which youngsters living overseas, who are putting all their effort into studying Japanese, are invited to express their opinions in Japanese. It’s not simply a one day event; participants (panelists) arrive in Japan about a month prior to the Nihongo Summit.
Everything is done in Japanese: peace studies at Hiroshima and Nagasaki; a cultural exchange with people living in the areas affected by the Great East Japan Earthquake; experiencing traditional Japanese culture; visiting corporations and politicians; and homestays. As part of the program, they get a chance to speak keigo, or honorific language, too. At the end of their visit they perform a presentation at the summit on “What I can do now for peace.”
Between 1999 and 2012 a total of 1,465 people applied to take part in the Nihongo Summit. From those, 233 panelists from 61 countries were selected to come to Japan.
Former panelists have maintained strong links to the organization by keeping in touch via Facebook and working in cooperation with JRP’s administration. Some return to Japan to study at university in a specialized field, while others work for Japanese companies overseas. A few have come back to Japan as diplomats.
The JRP’s other function is to give free lessons of Japanese language and culture to ambassadors and other diplomats stationed in Japan. JRP teachers teach their students to produce beautiful Japanese so that they can talk about their country in Japanese and use appropriate Japanese for work.
Miyoko, who was formerly a teacher of Japanese language, founded the JRP because she noticed that foreign children who had once lived in Japan ended up forgetting the Japanese they had learned once they returned to their countries. “Japanese is a compassionate language in which you put yourself in another person’s place. It’s a good language for discussing peace. Young people studying Japanese will build bridges between Japan and other countries in the future. And they’ll also contribute to world peace.” With this idea in mind Miyako ran the JRP in the early days with her own money.
Miyoko’s wish struck a chord with many and the number of sponsors has increased year by year. Eventually well-known companies within Japan and famous politicians began to cooperate.
Miyoko passed away in 2012. Miwa hesitated at first to take over when she discovered that the administration of the JRP, which depends on contributions, was quite a challenge. Her mind was made up, however, after listening to Miyoko’s passionate ideas. “I’ll do my best to keep the JRP going.”
Non-Profit Organization, The Japan Return Programme
Text: SAZAKI Ryo
[2013年4月号掲載記事]
特定非営利活動法人ジャパン・リターン・プログラム
「母がこれほど大きな仕事をしていたとは、実は知りませんでした」と特定非営利活動法人ジャパン・リターン・プログラム(JRP)の専務理事、池﨑美盤さんは言います。美盤さんは、母、美代子さんが1995年につくったJRPを、去年継ぎました。JRPの目的は、日本と外国のかけ橋となるような人材を育成することです。
JRPは二つの事業を行っています。一つは、1999年から毎年開いている「日本語サミット」です。これは海外で一生懸命に日本語を学んでいる若者を日本に招待して、日本語で意見を述べてもらうというイベントです。これは1日だけの発表会ではありません。参加者たち(パネリスト)は日本語サミットの約一月前に来日します。
広島や長崎での平和学習、東日本大震災の被災地の人たちとの交流、日本の伝統文化体験、企業や政治家への訪問、ホームステイなどを、すべて日本語でこなします。プログラムの中には、敬語で話す機会もあります。そして最後には、「今、平和のために自分ができること」をサミットで発表するのです。
日本語サミットに応募した人は1999~2012年の間に1,465人にのぼります。そのうち61ヵ国から233人のパネリストが選ばれて来日しました。
過去に参加したパネリストたちは、Facebookでの交流や運営に協力して、強い絆で結ばれています。また、日本に戻ってきて大学で専門分野を勉強したり、日系企業に就職したりしています。中には、外交官になって、戻ってきた人もいます。
JRPのもう一つの事業は、駐日外国大使館の大使や外交官に、無料で日本語や日本文化を教えることです。日本語で自分の国を紹介できるように、また、公務にふさわしい日本語を話せるように、JRPの日本語講師が美しい日本語を教えています。
日本語教師だった美代子さんがJRPをつくったのは、かつて日本にいた外国人の子どもたちが、せっかく覚えた日本語を母国に帰ると忘れてしまうことに気づいたからです。「日本語は、まず相手の立場に立って考えることのできる『おもいやり』の言語。日本語は、平和を語るのにふさわしい言語。そんな日本語を学ぶ若者たちは、将来きっと日本と外国のかけ橋になるに違いない。そして、世界平和にも貢献するはずだ」。そう考えた美代子さんは最初は自分のお金で運営していました。
美代子さんの熱意は多くの人の共感を呼び、賛同者が年々増えていきました。やがて、日本でよく知られた企業や有名な政治家が協力してくれるようになりました。
美代子さんは2012年に亡くなりました。美盤さんは寄付で成り立っているJRPの運営がとても大変なことを知って、最初は継ぐのをためらいました。しかし美代子さんの熱い想いを聞いて決心しました。「一生懸命JRPを守っていきます」。
文:砂崎良
-
[From March Issue 2013]

Origami Artist SHINGU Fumiaki
As an origami artist I’ve been asked by the government to promote the art of origami to the world by doing things like setting up a website that shows people how to make origami. Because it uses few natural resources, origami is eco-friendly. An outstanding example of “cool Japan” culture, it’s a pastime that both children and adults can enjoy.
Sometimes I’m asked to give lectures by universities overseas that specialize in the arts, but I’ve also started work on a big origami commission that I received from a Japanese person living in Europe. He said to me, “Though I brought a book on origami with me from Japan, it hasn’t captured the interest of children here. Could you please introduce me to origami that can capture the imaginations of European children.” With this in mind I made, “Origami for Christmas” and “Origami for Halloween.”
In western countries origami is regarded as a kind of paper craft. Origami is translated into English as paper folding, butrecently the word “origami” is more generally used.
The method of manufacturing paper was invented in China and brought to Japan in the early 7th century. Before long, manufacturing methods and materials used in Japan changed, producing durable, beautiful washi of excellent quality. Appreciated by the samurai classes, the use of washi spread, spawning a unique Japanese “paper culture.” In the early days, it was used for special envelopes that contained gifts of money; to express one’s hospitality. It was also used in daily life to create things like “shouji ” (sliding paper doors) and “fusuma” (sliding paper screens).
“Yuugi origami,” or the art of folding paper into things like cranes or helmets, and “unit origami ” constructing threedimensional out of identically shaped pieces of paper –popular in Europe – were invented in the Edo period (17~19 century). In the Meiji period the government invited the world famous German educator, Friedrich Wilhelm August FROEBEL, to Japan. He utilized origami in his child education program. This is how origami began to be taught in kindergarten.
In recent years, people in Hindu and Islamic societies have taken an interest in origami and I sometimes receive mail from them. They say that because it has no religious affiliations, origami can be easily accepted into their culture. It seems that my work will continue.
[2013年3月号掲載記事]
折り紙創作作家 新宮文明さん
私は創作作家として、国からの要請もあり、作品の作り方をインターネットに設けるなど、折り紙文化を世界に広めています。折り紙は大量の資源を使わず、自然と共存し、子どもから大人まで楽しめる娯楽で、「クールジャパン」の代表的なコンテンツの一つです。
今では海外の美術系の大学からときどき、講演の依頼が舞い込みますが、私が本格的に折り紙の創作を始めたのは、ヨーロッパに住んでいる日本人からリクエストがあったからです。「日本から折り紙の本を持って行きましたが、子どもたちが関心を持ってくれません。ヨーロッパの子どもたちが興味を持つ作品を紹介したい」ということでした。そこで、「クリスマスの折り紙」や「ハロウィンの折り紙」などをつくりました。
折り紙は、欧米でいうペーパークラフトの一部です。英語で、ペーパーホールディングともいいますが、最近はおりがみが一般的になってきました。
中国で発明された紙は、7世紀の初め頃、その製法が日本に伝えられました。まもなくして日本で製法や材料を変え、丈夫で美しく良質な和紙が誕生しました。和紙は武家社会に受け入れられてから急激に普及し、日本独特の紙文化が生まれました。初期はご祝儀袋などのような、おもてなしの心を表すものとして、また、障子やふすまなどの生活必需品にも使つかわれました。
江戸時代(17 – 19世紀)に入るとツルやかぶとなど、具体的な物の形に折る「遊戯折り紙」や、ヨーロッパで人気がある、特徴ある形に折ったものを組み合わせて立体的に作る「ユニット折り紙」が考案されました。明治時代に入ると政府から招かれたドイツの世界的な教育学者のフリードリヒ・W・A・フレーベルが、幼児教育のプログラムの一環として、折り紙を採用しました。これが幼稚園で折り紙を教える始まりです。
近年は、ヒンズー教やイスラム教社会でも関心が持たれ、ときどきメールが入ります。折り紙は宗教感がなく、受け入れやすいということでした。まだまだ、私の仕事は続きそうです。
-
[From February Issue 2013]
Public Interest Incorporated Foundation, National Foster Parent Association, Vice Chairman,
KINOUCHI HiromichiIn Japan there are some 40,000 children who are unable to live together with their families. This happens for a variety of reasons; sometimes because it would be inappropriate for them to live in an abusive environment. Many of those children live in care homes or nurseries. Only 10% live with foster families.
While UN guidelines recommend foster care for children who’ve been taken into care, it’s not yet very common in Japan. The government has just begun efforts to help support foster parents and is aiming to increase the percentage of children in foster care to 30% within the next ten years or so.
There are four kinds of foster parent in Japan: “child rearing foster parents” take care of children who, for whatever reason, can’t live with their parents; “specialist foster parents” take care of children who have been abused, or are mentally or physically handicapped; “parents hoping to adopt” who are aiming to adopt a child but haven’t yet done so; and “relations who are foster parents” – grandparents, uncles, aunts, and so forth. With the exception of relations who are foster parents, one becomes a foster parent with the approval of the governor of the prefecture. To become a “child rearing foster parent” or a “specialist foster parent,” training is obligatory.
In Japan, foster care isn’t very common yet, but why isn’t institutional care good enough? One reason is that life in care homes is centered around group activities. That makes it hard for children to develop individuality and to learn about family life and social rules, which they need to know about to become responsible members of society. Also, it’s hard to develop an emotional relationship with individual caregivers, attachments which children need.
So why is it that, in Japan, institutional care is so well established and has continued for so long at the expense of foster care? Some people point out that the public is generally unaware of the need for volunteers, but I think one of the reasons is the lack of government support for children who need care. Compared to institutional care homes, foster families require a lot of support from the system, but this support is sadly lacking.
As institutional care is the norm in Japan, we are hosting an IFCO (International Foster Care Organization) World Conference in Osaka in September this year in order to promote foster care. It’s an opportunity to discover what can be done to promote foster care and with this in mind, experts from around the world will be invited to participate.
The year before last, about 280 children lost both parents in the Great East Japan Earthquake. Most of them are living with relatives. They are being cared for by relying on the institution of “relations who are foster parents,” but some relatives are reluctant to register as foster parents as they themselves are struggling to get by.
After the Great Earthquake at the IFCO World Conference in Canada, we talked about the Japanese custom of making senbazuru (a thousand paper cranes) for disaster victims. Following this, Wanslea, an Australian foster care association sent 5,000 of these cranes together with messages of support to the National Foster Parent Association. And we sent these on to the people in the areas affected by the disaster; this made them very happy.
[2013年2月号掲載記事]
公益財団法人全国里親会
副会長 木ノ内博道さん日本には、家族と一緒に暮らすことのできない子どもが4万人ほどいます。虐待により家庭で暮らすことが適切でないなど、さまざまな事情があります。その多くは児童養護施設や乳児院で暮らしています。里親家庭で暮らす子どもは全体の1割にすぎません。
国連の指針では保護された子どもについても家庭養護をすすめていますが、日本ではなかなか進まないのが現状です。政府は10数年後に家庭養護を3割に増やす目標を立て、里親支援にも力を入れ始めています。
日本の里親制度には4種類あります。親の事情などで親と暮らせない子どもを預かる「養育里親」、虐待を受けたり、心身に障害があったりする子どもを養育する「専門里親」、養子縁組の目的で子どもを委託されたがまだ養子縁組に至っていない「養子縁組希望里親」、祖父母、おじ、おばなどが子どもの養育を行う「親族里親」です。「親族里親」以外の里親は都道府県知事の認定を受けて里親になることができますが、「養育里親」「専門里親」には一定の研修が義務づけられています。
日本では家庭養護がなかなか進みませんが、なぜ施設養護ではいけないのでしょうか。理由の一つは、施設では決まった日課を団体生活で行っていることです。このため自主性が育たず、社会人として自立していくための家庭モデルや社会のルールが学びにくいといわれています。また、子どもにとって必要な特定の養育者との愛着関係を築くことが難しいこともあります。
なぜ日本では家庭養護が広がらずに施設養護が長い間続けられてきたのでしょうか。国民のボランティアに対する意識の低さを指摘する人もいますが、私は保護を必要とする子どもへの行政の支援の立ち遅れがその一つだと思います。家庭養護は施設養護に比べてきめ細かな支援が必要ですが、その体制が十分ではありません。
施設養護の多い日本ですが、家庭養護を進めようと、今年の9月に大阪でIFCO(国際フォスターケア機構)世界大会の開催を進めています。世界中の関係者に集まってもらい、家庭養護の推進のための課題などを学んでいく機会にしたいと思っています。
一昨年の東日本大震災では280人ほどの子どもが両親を失いました。その多くは親族のもとで暮らしています。親族里親の制度を利用して養育されていますが、なかには親族自身の生活の見通しが立たずに、里親登録をためらっている人もいます。
大震災の発生後にカナダで行われたIFCO世界大会で、日本ではお見舞いに千羽鶴を折る習慣があることを話しました。すると後日、オーストラリアの里親支援機構ウオンズリの人たちから5千羽の折り鶴とメッセージが全国里親会に届けられました。そして被災地の里親に届けられ、たいへん喜ばれました。
-
[From February Issue 2013]
KAMIYA Toru
This artist custom-makes flutes from mass produced straws and in doing so, has created a sensation on TV with his performances. KAMIYA Toru, a resident of Takarazuka, Hyogo Prefecture, dreamed of becoming a recorder player while studying in the science department at Kyoto University, and, after graduating, threw himself into both performing and teaching the instrument.
At a training camp for the college of music he taught at, one of his students crushed the tip of a straw and accidentally made a sound. Kamiya recalls having a go at playing it himself but felt that, even though it was a wind instrument, when it came to producing a sound, he himself was only a beginner. He continues, “I was curious to see what kind of tones I could produce if I practiced.”
First he managed to play a scale by making finger holes in the straw. Then by trial and error he developed a range of flutes. For instance, to play low notes he needed a long straw, which he bent so his fingers could reach over the holes. With no one to play with, he struggled to create harmonies, but has now developed a flute on which he can play a solo quartet.
He has often appeared on television and performed at concerts overseas. In the US, he played the Japanese children’s song “Mushi no Koe” (Singing of Insects) on a flute shaped like a grasshopper. “After a few seconds, the tone becomes high-pitched like that of a grasshopper, before returning to normal. People were surprised by this unexpected change. I use different flutes depending on the song I play. I only played short pieces, things like children’s songs. My playing is also fun to watch, as some flutes have moving parts. I got the same response from the audiences abroad as I had had in Japan.” The flute for the song “Shabon-dama” (soap bubbles) is made in such a way that real soap bubbles emerge while he’s playing it.
During the Great Hanshin Earthquake his apartment block was completely destroyed. “I was at a loss, but my children said, ‘you’ll be all right with your straw flutes.’ It’s funny because there’s that phrase ‘to grasp at straws,’ and by rebuilding my life with straws, I had to do exactly the same. Because of my experience as a disaster victim, coupled with my desire to give people pleasure, I continue to give free concerts in the areas affected by the Great East Japan Earthquake.
“I think I’ve succeeded at improving my straw flutes because I’ve done other things in my life, so I’ve had all kinds of experiences and abilities to draw on. Since I have no predecessors, I’ve created a trail for others myself. It’s lonely and exhilarating at the same time. I’m happy that, wherever I go to play, people smile and enjoy themselves. I want to go on giving concerts and creating flutes that make audiences happy,” Kamiya says with a bright smile.
Text: KAWARATANI Tokiko
[2013年2月号掲載記事]
神谷徹さん
市販されているストローを笛に加工して演奏し、テレビ出演や公演で話題を呼んでいるアーティストがいます。兵庫県宝塚市に住む神谷徹さんは、京都大学理学部在学中からリコーダー奏者への道を志し、卒業後は演奏家と指導者として活躍していました。
指導している音楽大学での合宿で、一人の学生が何げなくストローの先をつぶして音を出しました。神谷さんも吹いてみたところ、これはストローで作った管楽器だが、自分ではまだ初心者レベルの音しか出せないと感じたと話します。「では、訓練すればどんな音色になるのだろうと、好奇心がわいてきました」と神谷さんは続けます。
まず、指で押さえる穴を開けて音階が出せるようになりました。低音を出すための長い笛では、曲がるストローを使って指が穴に届くようにするなど、すべて一人で工夫しながら笛を開発してきました。共演者がいないので合奏はできませんが、なんとかハーモニーを奏でたいと苦心して、今では一人で四重奏が演奏できる楽器まで生まれました。
海外でのテレビ出演や、公演もたびたびあります。アメリカ公演では、日本の童謡「虫の声」を、バッタの形をした笛で演奏しました。「何秒か吹くと、曲の途中で本当に虫が鳴くような高い音色に変わり、またもとの音色に戻ります。その意外性にとても驚かれました。演奏する曲ごとに専用の笛を使います。童謡などの短い曲ばかりで、演奏しながら動くしかけもあるので、見ても楽しく、反応は日本と変わらない印象でしたね」と神谷さん。「しゃぼん玉」という曲では、演奏中に実際にしゃぼん玉が出る仕組みになっています。
阪神大震災のときには、住んでいたマンションが全壊しました。「途方に暮れましたが、子ども達から『お父さんにはストロー笛があるから大丈夫だね』と言われたんです。『わらにもすがる』ということわざがありますが、ストロー(日本語では「わら」)の楽器で生活を再建するとはことわざ通りでおもしろいなと感じました」。自身が被災した経験と、公演を楽しんでもらいたいという気持ちから、東日本大震災で被災した地域でのコンサートを、無料で引き受ける活動を続けています。
「寄り道をしてきたから得られた、様々な経験や能力を活かしてストロー笛を発展させた気がします。先人がいないので、自分が歩いたところが道になります。孤独でもあり、清々しくもあります。どこへ行って演奏しても、人が笑って楽しんでくれるのが嬉しいですね。これからもお客さんに喜んでもらえる笛の開発とコンサートを続けていきたいです」神谷さんは、晴れやかな笑顔で話します。
文:瓦谷登貴子
-
[From January Issue 2013]
KAWAKAMI Jinichi
Since way back, ninja have appeared in novels, movies, comics and games. Using their ninjitsu skills, ninja fight enemies and save their masters who employed them. Similar to a famous brand, the ninja is known, not only in Japan, but also abroad. What isn’t known though is whether such people really existed, and if they did, what kind of activities they were involved in.
In Japan, Iga City, Mie Prefecture and Koka City, Shiga Prefecture are famous as ninja hangouts. In order to do research into the history and culture of ninjutsu, KAWAKAMI Jinichi, honorary director at the Iga-ryu Ninja Museum in Iga City, became a specially appointed professor of the Science of Ninjutsu at Mie University last December. Kawakami says, “Since I was a child, I’ve been practicing the same training routines as ninja.”
When he was around six, Kawakami encountered ISHIDA Masazo, teaching Koka-ryu ninjutsu in his neighborhood. Taking an interest in ninjutsu, he learned a variety of martial arts techniques used by ninja, including how to throw shuriken (throwing stars), a weapon commonly believed to have been used by ninja. He also learned to walk without making any sound, to use wild grass as medicine, to sneak into enemy territory, and to set traps. And at the age of 18, he succeeded Ishida and began to hand down the Koka-ryu ninjutsu tradition and teach martial arts to young pupils as a master himself.
Called “the last ninja” by those got to know him through his ninja activities, Kawakami speaks at various seminars. It was because of a lecture he gave at a symposium hosted by Mie University last year that Kawakami became a specially appointed professor. At the university, he is studying documents related to ninjustu. He is planning to publish his research results in the future.
Running and jumping about in the mountains, fighting with ninjitsu, and so on; in novels and movies, ninja are depicted as being similar to spies. Kawakami, however, sees ninja as people who have knowledge about information gathering, psychology, medicine and sociology, as well as survival skills. Therefore, when he gets injured or catches a cold, Kawakami cures himself with medicine made from wild grasses.
“When I was training to become a ninja, I practiced reading other people’s emotions, and this was useful when making business deals and for establishing important relationships,” Kawakami recalls. Because of this, he says, “At the university, I want to teach students not only about the skills that ninja possess, but also their way of thinking, their spirit and historical background.”
Kawakami is trying to portray ninja not as fictional characters but as masters of survival skills that can be applied to modern life. And in order to disseminate this idea, he is working as a museum director and a university professor. Kawakami’s science of ninjutsu, might help people from abroad with an interest in Japanese culture, history and thought processes, to know Japan more deeply.
Text: ITO Koichi
[2013年1月号掲載記事]
川上仁一さん
忍者は昔から小説や映画、まんが、ゲームなどの題材として登場します。忍者は忍術を使って敵と戦ったり、雇い主である主人を助けたりします。日本国内はもちろん、海外でも「ニンジャ」という一種のブランドとして知られています。しかし、そういう人たちが本当にいたのか、いたのならどのような活動をしていたのかはあまり知られていません。
日本では三重県伊賀市と滋賀県甲賀市が忍者の里として有名です。このうち、伊賀市にある伊賀流忍者博物館の名誉館長、川上仁一さんは昨年12月、忍術の歴史や文化などを研究するため、三重大学で忍術学を研究する特任教授になりました。川上さんは自分のことを「小さいころから、忍者が行った修行を積んだ者です」と言います。
川上さんは6歳頃のとき、家の近所で甲賀流忍術を伝えていた石田正蔵さんに出会いました。忍術に興味を持った川上さんは、一般に、忍者が使ったとされる武器である手裏剣や様々な武術などを学びました。また、音を立てずに歩く方法、薬の代わりに野草を使う方法、敵地への潜入、謀略の技なども身に付けました。そして、18歳のときに石田さんのあとを継いで甲賀流忍術を伝承し、武術では後輩を指導する師範になりました。
川上さんは忍者の活動を通じて知り合った人々から「最後の忍者」と呼ばれており、さまざまな講演会などで話をしています。川上さんが三重大学の特任教授になったのも、三重大学が昨年開いたシンポジウムで講演をしたことがきっかけとなりました。大学では忍術に関する資料の研究などをしています。将来はその成果をまとめていく考えです。
小説や映画などで忍者は、野山を駆け巡り、飛んだり跳ねたり、忍術をかけたりするスパイのように描かれています。しかし、川上さんは忍者を、情報収集や心理学、薬学、社会学の知識を備えたサバイバルの技術を持った人のことと考えています。ですから、川上さんはけがをしたり風邪をひいたりしたときも自分で野草を薬にして治します。
また、川上さんは「忍者の修行をしていたときに、相手の気持ちを上手に読む訓練をしたので、仕事で駆け引きをしたり、大事な関係を築いたりするときに役立ちました」と振り返ります。このため「大学では、忍者の持つ技術的なことばかりでなく、忍者の考え方や精神、歴史的な背景なども学生に教えていきたいです」と話しています。
川上さんは、忍者を架空の存在ではなく、現代にも応用できるサバイバル技術の伝え手としてとらえようとしています。そして、その考え方を広めるために博物館の館長や大学の教授を務めています。川上さんの教える忍術学は、日本の文化や歴史、考え方などに興味を持つ外国人にとっても、日本をより深く知る手助けになるかもしれません。
文:伊藤公一
-
[From December Issue 2012]
Guy TOTARO, The Smile Ambassadors
After nearly 25 years in the entertainment business, Gaetano “Guy” TOTARO is a performing “jack of all trades.” A native of California, Guy graduated from San Francisco State University in 1989 with a BA in Acting and Theatre Arts. He continued his training with the award-winning San Francisco Mime Troupe and at the world famous Ringling Bros. and Barnum & Bailey’s Clown College.
Then, in 1993, work opportunities brought Guy to Japan, where he spent five years building a reputation as one of the most versatile foreign tarento in Tokyo, performing as a variety entertainer, actor, narrator and model. After another seven years back in the States doing similar work, Guy was once again drawn to Japan – this time settling down in Tokyo to start a family.
“Since coming back to Japan in 2005, I’m very proud to have been Suntory’s ‘Mr. CC Lemon’ and have been fortunate to have had many other high-profile roles in commercials, educational and music videos, and as a voice actor,” Guy says. He is also kept busy with his educational workshops, and provides creative consulting for entertainers and theme parks. Arguably Guy’s most important role, however, came after the Great East Earthquakes in March 2011.
“In April 2011 I traveled north for the first of what would turn out to be many relief tours. I went to a shelter, a day care center, a church and a junior high school in Iwate Prefecture. I found kids big and small who hadn’t laughed or even smiled in over a month,” Guy says. “It was clear that my silly shows and circus workshops were an effective tool to combat PTSD issues and it was even clearer that I needed to return and continue.”
Shortly after getting back to Tokyo, Guy was contacted by the Tyler Foundation, an NPO that provides support for pediatric cancer patients and their families, with whom he had collaborated before.
“Together we created the ‘Shine On! Smile Ambassador Program.’ The Tyler Foundation provided the logistical and financial support and I created and facilitated the program content,” Guy explains. “From April 2011 to the end of March 2012, we visited more than 80 unique locations and I interacted with almost 8,000 kids. Without their help I could have never reached as many people as I did in that first year.”
That collaboration ended this past March, but Guy is now working to register Niko Niko Taishi (The Smile Ambassadors) as a new NPO. Guy uses the plural Ambassadors because he believes we can all work together to make a big impact on the people of Tohoku and beyond.
“The Smile Ambassadors’ goals are to continue to offer PTSD relief to the kids, teachers and communities we’ve reached previously; to train teachers, caregivers and parents how to recognize PTSD and facilitate care; to be ready to mobilize and act in the case of any future traumatic events; and to help other populations in need at orphanages, hospitals and women’s shelters,” Guy says.
Text: Thomas TYNAN
[2012年12月号掲載記事]
ニコニコ大使 ガイタノ・トタロさん
タレントのガイタノ・トタロさん(通称ガイ)は、なんでも屋をしています。これまでの25年間、エンターテイメント業界でさまざまな仕事をしてきました。ガイさんはアメリカ・カリフォルニア出身で、1989年サンフランシスコ大学で演劇博士号を取り、卒業しました。その後は、受賞歴を持つサンフランシスコ・マイム団で、また、世界的に有名なリングリング・ブラザーズ・バールナン・エンドベーリークラウンカレッジでトレーニングを受けました。
その後、1993年にガイさんは仕事で日本へやってきました。そして東京で5年間過ごし、バラエティーエンターテイナー、俳優、ナレーター、モデルとして活躍し、最も多才な外国人芸人の一人としての地位を築きました。アメリカに戻り、7年間同じような仕事をした後、再び日本へやってきました。そして家族を持ち、東京に落ち着きました。
「2005年に日本へ戻ってから、運よく声優としてサントリーの『ミスターCCレモン』をはじめ、多くのコマーシャルや教育、音楽ビデオで注目される役割を果たすことができ、誇りを持っています」とガイさんは言います。教育ワークショップ、エンターテイナーやテーマパークのための創作コンサルティングなどでも多忙です。しかし2011年3月に起こった東日本大震災の後、ガイさんにとって間違いなく最も大切な役割がやってきました。
「2011年4月、北へ向かいました。これが後に多くの慰問ツアーとなる最初でした。岩手県の避難所、デイケアセンター、教会、中学校を訪れました。大きい子も小さい子も1ヵ月以上もの間、声に出して笑うことはもちろん、ほほえむことさえなかったのです」とガイさんは話します。「私のたわいのないショーやサーカスのワークショップがPTSD(心的外傷後ストレス障害)に効果的な方法であることは明らかで、私がそこに戻って続けることが必要なことがさらに明らかになりました」。
東京に戻ってすぐに、NPOのタイラー基金から連絡がありました。この基金は小児がんの患者や家族を支援していますが、ガイさんは以前にもコラボしています。
「私たちは一緒に『シャイン・オン!ニコニコ大使プログラム』をつくりました。タイラー基金は物流と金銭の支援をし、私はプログラムのコンテンツを考え、つくりました」とガイさんは説明します。「2011年4月から2012年3月末にかけて80ヵ所以上を訪れ、ほぼ8,000人の子ども達と交流しました。その援助がなければ、最初の年から多くの人に出会うことは決してできませんでした」。
コラボは今年3月に終了しましたが、ガイさんは新しいNPOのニコニコ大使として今も登録し、働いています。ガイさんは複数の大使になっています。東北やその周辺の人々を元気づけるためにみんなが一緒に働けると信じているからです。
「ニコニコ大使のゴールは、以前出会った子どもたちや、先生、地域の人たちからPTSDを取り除いてあげること、先生や介護人、親たちにPTSDをどのように受け止め、治療を促進するかを教え続けていくことです。起こりうるトラウマ問題に人を動員して行動したり、養護施設や病院、女性シェルターで必要としている人たちを助ける準備をしています」と、ガイさんは話します。
文: トマス・タイナン
-
[From October Issue 2012]
Pradahan VIKAS
“Actually, I did not know what Twitter was,” confesses Pradahan VIKAS honestly. “And still, I do not understand how it really works.” Vikas, originally from Nepal, is a chef. He runs a restaurant located in Itabashi Ward, Tokyo. Because Vikas’ restaurant is famous on Twitter, customers visit from all over Japan, forming a queue in front of his restaurant.
“The reason why my restaurant is doing so well is all thanks to the kindness of the Japanese people,” says Vikas. When he opened the restaurant, there were hardly any customers. His tweets like, “I hand out fliers, but no customers come,” and “What will become of Vikas if this keeps up?” elicited sympathetic comments and were retweeted over and over again. As a result, his followers grew to almost 80,000 and huge numbers of customers began to show up.
Vikas came to Japan in 1995 and started working at an American restaurant. “When I was in Nepal, I heard that jobs in Japan were very easy; that all the hard labor was done by machines. But the reality was completely different. Yes, there was a dishwasher, but Japanese people pay close attention to detail, so even the smallest speck left on a dish is not tolerated. That’s why the dishes need to be rinsed off before putting them in the dishwasher. I was washing dishes from morning till night. It was really tough.”
After a few months of this he finally said that he wanted to quit. Then the head chef apologized for making him just wash dishes and began teaching him how to cook. “If I had not met the head chef, I probably would never have become a chef. He never got angry, but taught me by telling me, ‘it’s delicious;’ by encouraging my efforts,” Vikas reflects.
As a result of his hard work, Vikas became so good that soon people started to say, “We can’t trust anyone but Vikas when it comes to cooking meat.” One day, someone said, “You can make curry since you are Nepalese, right?” So he was suddenly called upon to make curry. The curry was popular with customers and became a regular item on the menu.
Before long the head chef left. Then Vikas soon became a victim of bullying. He could not take it anymore, so he too left the restaurant. “Thanks to that, I was able to work at a different restaurant and gain more experience. So, I think the bullying was all part of God’s plan for me,” says Vikas.
In 2010, Vikas opened his own restaurant. “Everyone has a small dream. When that dream comes true, people work hard to achieve their next dream.” Vikas’ Japanese friends who were concerned about Vikas tweeted his comments and created a logo and website for his restaurant. The restaurant got back on track, and he was able to open a second restaurant in Harajuku this May.
Vikas named his restaurant “Daisuki Nippon” (I Love Japan). The walls of the restaurant are decorated with messages from customers like, “Mr. Vikas has a wonderful personality,” and “His warm Tweets are very comforting.” Vikas, who loves Japanese, is loved in turn by many Japanese people.
Text: SAZAKI Ryo
[2012年10月号掲載記事]
プラダハン・ビカスさん
「実は、ツイッターがどういうものか知らなかったんですよ」。プラダハン・ビカスさんは正直に言います。「そして今も、しくみがあまりわからない」。ビカスさんはネパール出身のシェフです。東京都板橋区でレストランを経営しています。ビカスさんの店はツイッター上で有名で、日本全国からお客が来て行列ができるほどです。
「うちの店がうまくいったのは日本の人たちがやさしいからです」とビカスさんは話します。開店したころ、ほとんどお客が来ませんでした。「ちらし くばりましたが おきゃくきません」「このままだと びかす どうなっちゃうだろ」というビカスさんのツイッターが同情的なコメントと共に何度もリツイートされました。その結果、フォロワーが8万人近くまで増えてお客がたくさん来るようになったのです。
ビカスさんは1995年に来日し、アメリカンレストランに就職しました。「ネパールにいた頃、日本での仕事はとても楽だと聞いていました。きつい労働は全部機械がやってくれると。現実はまったく違いました。確かに食洗機はありましたが、日本人は細かいのでちょっとの汚れも許しません。だからお皿は食洗機に入れる前に一度手洗いするんです。毎日朝から晩までお皿を洗いました。本当につらかったです」。
数ヵ月後ビカスさんはついに辞めたいと言いました。すると料理長は、皿洗いだけさせて悪かったと謝って、料理の作り方も教えてくれるようになりました。「その料理長に出会わなかったら、私は料理人になっていないと思います。けして怒らず『おいしい』とほめて育ててくれました」とビカスさんは振り返ります。
がんばった結果ビカスさんは、「肉を焼くのはビカス以外任せられない」と言われるほどの腕前になりました。あるとき「ネパール人ならカレーが作れるでしょう」と言われて突然カレーを作ることになりました。そのカレーは評判がよく、店のメニューの一つになりました。
やがて料理長が退職しました。するとある人がビカスさんをいじめるようになりました。耐えられなくなってビカスさんも店を辞めました。「おかげで他の店へ転職して、いい経験を積めたんですよ。だからいじめも神様が計画してくださったことだと思っています」とビカスさんは言います。
2010年、ビカスさんは自分の店を出しました。「誰だって小さい夢が一つあるでしょう。それがかなったら次の夢に向かってがんばるのです」。日本人の友人たちが心配して、ビカスさんのコメントをツイッターで公開したり、店のロゴやサイトを作ってくれたりしました。店は軌道に乗り、今年5月には原宿に2号店を出すことができました。
ビカスさんは店に「だいすき日本」という名前をつけました。店にはお客の書いた「ビカスさんは人柄もすてきです」「あたたかいツイッターにいつも癒されています」というカードがたくさん飾ってあります。日本人が大好きなビカスさんは、日本人にも好かれています。
文:砂崎良
-
[From July Issue 2012]
HONBORI Yuji
This artist makes Buddhist images out of discarded corrugated cardboard. HONBORI Yuji who lives in Kobe, Hyogo Prefecture, studied sculpture at Aichi Prefectural University of Arts and, after completing graduate school, has been constructing works made out of junk and construction waste. “The Great Hanshin Earthquake completely destroyed my house and when I saw the damage to the surrounding area, I was completely shocked. Since then I’ve felt some reluctance about using fresh timber as a raw material.”
Moving to a new location, he spent days searching for the right material, experimenting with soil, wood chips, and so forth. “On one occasion I made a sculpture of a likeness of a zushi (miniature shrine to display Buddhist images) with scrap wood taken from an old shrine. The shape of the left over wood unexpectedly resembled a Buddhist statue. This incident was the impetus for me to create my first work by dissolving a milk carton in water and pouring it into a plaster mold to make a Buddhist statue. After that, I finally hit on the idea of using discarded corrugated cardboard as a material,” says Honbori.
It takes about a month and a half to make a 160 centimeter Buddhist image. One characteristic of these works is that, from the side, you can see colored text printed onto the corrugated cardboard, which has been intentionally left that way. And from the front, through undulating spaces in the cardboard, you can see right through to the back. A circle has been created in the center of the Buddha; a void made from poured concrete. This resembles a tainaibutsu (a small Buddhist statue placed within a larger one), a devotional kind of statue that dates from the Heian period.
“It would make me happy if people want to see traditional Japanese Buddhist statues after viewing mine. I make statues based on my own mental image, but I have difficulty walking that fine line of creating a form that is just about recognizable. But that is also why the production process is enjoyable,” Honbori says.
In March this year, his works were exhibited at ART FAIR TOKYO for the second time. They were displayed in the same space along with joumon doki (straw rope-patterned ancient Japanese pottery) and ancient Buddhist statues. This juxtaposition attracted a great deal of attention. “I used the eleven-faced Kannon (Goddess of Mercy) of Shorinji Temple in Nara as the model for my work. Although these are modern art works made of corrugated cardboard, I realized that their charm could be seen in a new light if they were exhibited with art works from antiquity that were of national treasure quality,” Honbori says. In May, he also participated in the Hong Kong International Art Fair, the biggest Art Exhibition in Asia.
“When I see people putting their palms together in prayer in front of my work, I realize that because I’m making an image of Buddha, I can’t create half-hearted works. With a playful heart, I want to continue making pop art,” says Honbori, who continues to challenge audiences with his works.
Text: KAWARATANI Tokiko
[2012年7月号掲載記事]
本堀雄二さん
捨てられた使用済みのダンボールを素材に、仏像を作るアーティストがいます。兵庫県神戸市に住む本堀雄二さんは、愛知県立芸術大学で彫刻を学び、大学院を卒業後は廃品や建築廃材を使った作品作りを発表していました。「阪神大震災で自宅が全壊して、周囲の被害の状況を見て大きなショックを受けました。それ以来、素材として木材を使うことに抵抗を感じるようになったのです」と本堀さんは話します。
移転した土地では土を使ったり木くずを利用したりと素材探しの日々が続きました。「あるとき、神社の廃材で厨子(仏像を安置する仏具)をイメージした作品を作ったときに、最後に残った部分が、その偶然できた形に仏像の姿を感じました。この出来事がきっかけで、牛乳パックを溶かしたものを石こうの型に流し込んで、一体の仏像を仕上げたのが最初です。その後、使用済みのダンボールを使うことにたどり着きました」と本堀さんは続けます。
160センチの仏像1体に、約1ヵ月半の制作日数がかかります。横側からは、あえて残しているダンボールの色の文字が見え、真正面からはダンボールの断面にある波状の空洞により、背後が透けて見えるのが特徴です。仏像の中央には、コンクリートを流し込む建築材料のボイドを使った輪が入っています。平安時代から仏像のなかに納められているとされる「胎内仏(仏像の胎内に納められている小仏像)」をイメージしています。
「日本に古くからある仏像を見たいと思ってもらえたら嬉しいですね。自分のなかでイメージした仏像を元に作りますが、これ以上つきつめたら形がわからなくなるというぎりぎりのラインを生み出すのが、毎回難しいです。そこがまた楽しみでもありますね」と本堀さん。
今年の3月には日本最大の美術の展示会、アートフェア東京に2回目の出展をしました。縄文土器や古来の仏像と同じスペースで展示され、そのコラボレーションが大きな注目を集めました。「奈良にある聖林寺の十一面観音をモデルにしました。素材がダンボールの現代美術ですが、国宝級の古い美術品と一緒に展示できるのが、この作品の魅力だと再認識しましたね」と本堀さんは話します。5月にはアジア最大の美術の展示会、香港アートフェアにも出展しました。
「作品に手を合わせてくれる人を見ると、仏像を作っているのだからいい加減な作品作りはできないなと思います。遊び心も大事にして、ポップな作品を作り続けたいですね」。本堀さんの作品への挑戦は続きます。
文:瓦谷登貴子
-
[From June Issue 2012]
Japan is a country that holds great fascination for architects. There is something unique about Japan and its architecture, whether it be traditional or contemporary. For a country with a reputation of being conservative, it gives rise to some of the world’s most extraordinary architecture. There seems to be a lack of inhibition that offers architects freedom of expression. There are buildings that seem to serve no purpose. They are simply pieces of urban artwork. In these cases, form certainly does not follow function.
For me, the fascination with Japanese architecture began after I graduated and went to work in Japan. It was the early 1990s and the end of the property bubble. There were some remarkable projects being built by Japanese and foreign architects. Around that time renowned architecture publication, “Japan Architect,” published an edition specifically on Tokyo which contained architectural walking maps. Armed with these walking maps, I spent most weekends seeking out the latest architectural wonder or historic classic.
After I returned to Australia and established my own architectural practice, I maintained a strong connection with Japan. I was able to undertake some projects in Japan and followed the latest news in the Japanese architecture scene. My appreciation and knowledge of Japanese architecture has developed to the point where I now conduct Japan Architecture Tours. On the tours I share my knowledge, appreciation and understanding of Japanese architecture with architects and other people with a general interest in architecture.
There are so many great places to visit in Japan where one can see excellent examples of Japanese architecture. There is Ginza and Omotesando, home to the boutiques of some of the greatest fashion brands in the world; there are the open-air architectural museums such as Meiji-Mura, Nihon Minkaen and Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum which contain old buildings and houses which help us understand Japan’s architectural historical past.
There are the museums and galleries around Roppongi, the skyscraper district of Shinjuku, there is Kyoto, home to UNESCO World Heritage buildings and structures such as Katsura Rikyu, Nijo-jo, Kiyomizu-dera and Kinkaku-ji; there are the quaint little backstreets and alleys that have survived since the Edo period; and of course there are plenty of other wonderful architectural gems dotted throughout the urban landscape. Where else could you see so much architectural variety and history?
Japan is considered by many architects to be at the forefront of architectural design expression. The ever-changing urban and architectural landscape of Japan means there is so much to see on the Japan Architecture Tours. This combined with the warm welcome and generous hospitality, makes it a joy to visit Japan every time.
Text : Robert DAY
[2012年6月号掲載記事]
日本は建築家にとってとても魅力的な国です。伝統的なものから現代的なものまで、日本と日本建築には何かユニークなものがあります。保守的な国、との評価がありながら、いくつかの世界でもトップクラスの驚異的な建築を生みました。心理的抑制がないことが、建築家に表現の自由を与えているようです。何も目的がないような建築物もあります。単なる都市の芸術作品です。そのようなケースでは、もちろん形は用途とは関係ありません。
私が日本建築のとりこになったのは、学校を卒業して日本へ働きに行ってからでした。それは1990年代のはじめで不動産バブルが終わった時期でした。日本人と外国人の建築家が手がけていたすごいプロジェクトがいくつかありました。その頃、有名な建築雑誌「JA」が建築物散歩地図を収めた東京特集号を出しました。その地図を持って、私はほとんどの週末を最新の建築物や歴史的建築物を訪ねて過ごしました。
オーストラリアへ帰国して自分の事務所を開いた後も私は日本との深い関係を保ちました。日本でいくつかプロジェクトを手がけることができ、日本建築界の最新情報をフォローしました。日本建築に対する私の評価と知識は、今では日本建築ツアーを主催するほどになりました。ツアーでは、建築家や建築に関心のある人達に、日本建築に関する自分の知識・評価・理解を伝えます。
日本には優れた日本建築の例を見られる良いところがたくさんあります。世界一流のファッションブランドの店が並ぶ銀座と表参道があります。日本建築史の理解に役立つ古い建物や家屋がある明治村、日本民家園、江戸東京たてもの園といった屋外建築博物館もあります。
六本木周辺には博物館やギャラリーが、新宿には高層ビル街があります。桂離宮、二条城、清水寺、金閣寺といったユネスコ世界遺産の建物や構造物がある京都もあります。ここには江戸時代から生き残った古風で細い裏通りや小路があります。それにはもちろん都市の風景に点在する他の素晴らしい宝石のような建築物もあります。これほど多彩な建築や歴史を見られるところが他にあるでしょうか?
多くの建築家が日本の建築デザイン表現は最先端にあると考えています。日本の都市と建築の風景は常に変化していて、日本建築ツアーでは見るものがたくさんあります。それに加え、あたたかく歓迎され、寛大にもてなしてもらえるのですから日本を訪れるのは毎回楽しみです。
文: ロバート・デイ
-
[From June Issue 2012]
Carl ROBINSON
New Zealander Carl ROBINSON is the CEO of Jeroboam Co., Ltd., a wine importing business based in Japan. “In the wine business,” he says, “the people you meet are happy to see you.” Being a social animal, he’s just as happy to meet people. A natural communicator, since coming to Japan in 1990, Robinson acquired his language more through immersing himself socially, than studying textbooks.
“I still think immersion is a good thing because you just have to figure it out,” he says. Robinson originally came to Japan with his wife for a working holiday. One option was to stay in Tokyo as English teachers – they could make a little more money, but maybe experience less of the language and the culture. Instead, they did the exact opposite: for six months they lived as the only foreigners in a small town in Oita Prefecture.
“It was certainly tough not having anyone to help you, but it was also very, very satisfying once you started to realize that people could understand you.” Robinson admits he’s no “kanji freak” totally focused on studying, so ultimately, the desire to interact drove him to improve his Japanese. “I certainly wanted to communicate with the people I was working with and the people I was seeing every day.”
After that half year, Robinson and his wife moved to the UK. But they still loved Japan, and six years later they arranged a transfer for Robinson’s wife to her employer’s Tokyo office. Robinson, who had been working in the wine business, found a job as a sommelier for the Tokyo American Club. The timing was perfect. “We came back here in 1996, and it was just at a time when wine was starting to take off in Japan.”
After eight years of consulting and organizing events, Robinson chose to move into importing. As CEO of Jeroboam, he says, “I needed to improve my formal Japanese and to learn a lot of technical language that I hadn’t been exposed to before.” In deals with bankers and lawyers, he enlists the help of bilingual staff. “Because you don’t want to make mistakes in situations like that.” Still, all internal communications are in Japanese. “It’s important to have your own style, especially if you’re running a company,” he says.
Robinson’s Japanese has been put to the test under stressful situations. Last March, Robinson was at work when the Great East Japan Earthquake struck. “It was certainly challenging when you’re making decisions that seriously affect other people,” he says. And before that, Robinson faced a crisis of a different kind: the economic shock of 2008. He had to use his Japanese to nurture his employees during uncertain times, both to lead and to inspire. “It really pushes your Japanese ability.”
It’s situations like these that reinforce Robinson’s philosophy. Relying too much on memorization, he believes, gives too much emphasis on language structures and gets in the way of what you’re trying to say. The best way to learn, for Robinson, is total immersion. His one recommendation for students of Japanese is to go to a place where they can be totally surrounded by the language. “It’s tough,” he says, “but it’s a good way to learn.”
Text: Gregory FLYNN
[2012年6月号掲載記事]
カール・ロビンソンさん
ニュージーランド人のカール・ロビンソンさんは日本に本社があるワイン輸入会社、ジェロボーム株式会社の社長です。「ワインの商売をしていると会う人に喜ばれます」とロビンソンさんは言います。社交性に富むロビンソンさんは人に会うのが好きです。生まれつき話上手のロビンソンさんは、1990年に日本へ来て以来、教科書で勉強するより人とのつきあいのなかで日本語を身につけました。
「意味を理解するには、今も日本語漬けになるのはいいことだと思っています」とロビンソンさんは言います。ロビンソンさんは最初、ワーキングホリデーのために夫人と一緒に来日しました。ひとつの選択肢は英語教師として東京に滞在することでした。そうしていれば少し多めにお金を稼げたでしょうが、日本語と日本文化の経験は減っていたかもしれません。その代わりに二人は正反対のことをしました。他に誰も外国人がいない大分県の小さな町に6ヵ月間住んだのです。
「助けてくれる人がいないのは確かに大変でしたが、人に理解されているということがわかり始めると、すごくやりがいを感じました」。ロビンソンさんは勉強のことしか頭にない「漢字狂」ではないと認めていますが、結局もっと交流したいという気持ちが日本語の上達を後押ししたのです。「一緒に働いている人達と、また毎日会う人達とどうしても交流したかったのです」。
その半年後、ロビンソンさんと夫人はイギリスへ引越ました。でもまだ日本が好きだったので、6年後、夫人が勤務している会社の東京支社に転勤できるようにしたのです。ワイン業界で働いていたロビンソンさんは、東京アメリカンクラブでソムリエの仕事を見つけました。絶好のタイミングでした。「私達は1996年にここに戻って来たのですが、ちょうど日本でワインがブームになり始めた頃だったのです」。
コンサルティングとイベント開催の仕事を8年間した後、ロビンソンさんは輸入の仕事に移りました。ジェロボームの社長として「敬語をもっと身につけたり、以前は自分に関係なかった技術用語もたくさん覚えたりする必要がありました」。銀行員や弁護士とのやりとりには日英のバイリンガルスタッフの助けを借ります。「そういう場ではミスはしたくないですから」。でも社内の意思疎通は全て日本語です。「自分のスタイルを持つことが重要です。特に会社を経営しているなら」とロビンソンさんは話します。
ロビンソンさんの日本語は、ストレスのたまる状況で試練に立たされてきました。昨年3月東日本大震災が起きた時、ロビンソンさんは職場にいました。「他の人達に深刻な影響をおよぼす決定を下すのは、確かにやりがいがありました」と言います。その前にもロビンソンさんは別の危機に直面していました。2008年の経済ショックです。ロビンソンさんは不安定な時期に従業員をはげますため日本語を使わなくてはなりませんでした。指揮するため、また元気を与えるためでした。「本当に日本語能力が伸びます」。
ロビンソンさんの信念を強固にしたのはそうした状況でした。暗記に頼り過ぎると、構文に重点がおかれて言いたいことが言えなくなると考えています。ロビンソンにとって一番良い習得法は日本語にひたり切ることです。日本語学習者に勧めるのは、日本語に完全に囲まれる場所へ行くことです。大変ですが良い習得法だと話します。
文:グレゴリー・フリン
Information From Hiragana Times
-
 March 2026 Issue
February 24, 2026
March 2026 Issue
February 24, 2026 -
 February 2026 Issue
January 21, 2026
February 2026 Issue
January 21, 2026 -
 January 2026 Issue – Available as a Back Issue
January 15, 2026
January 2026 Issue – Available as a Back Issue
January 15, 2026